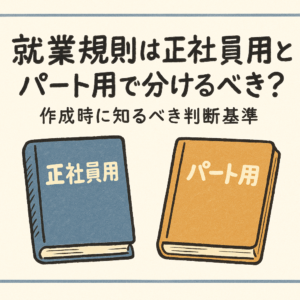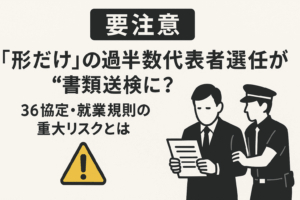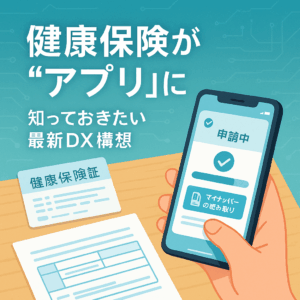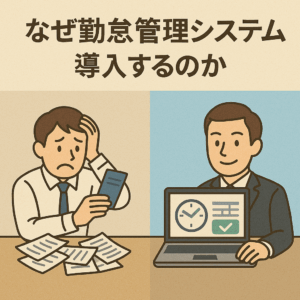【経営者様必見】行政調査 ~種類とポイント~

こんにちは、社会保険労務士の安生です。
行政調査と聞いて皆さんは何を思い浮かべますでしょうか?
「税務調査」はよく耳にすることが多いかもしれませんが、労働法や社会保険各法に関する調査と言うのはあまり馴染みのない方が多いかもしれません。
コロナ過以降、中断されていた行政調査が最近復活し、労基署や年金事務所から調査の依頼が届いて慌てる経験をされた方もいらっしゃるかもしれません。
今回は行政調査について触れていきたいと思います。
行政調査の代表格「労働基準監督署編」
労働法分野で行政調査というと「労働局」が対応するものと「労基署」が対応するものと範囲が異なります。
行政調査の代表格になる「労基署」の調査については主に以下の項目について調査を実施し、法違反があれば「是正勧告」、必要に応じて「指導票」を交付して改善指導などを行います。事案によっては行政警察官として「犯罪捜査」を行う権限まで持っています。
・労働基準法違反
・労働安全衛生法違反
・最低賃金法違反 等
これに対して「労働局」が対応するものとしては主に以下の項目が挙げられます。
・管轄労基署の管轄を超える広域事案
・重大悪質事案の処理方針
・労働施策総合推進法(ハラスメント各法)
・労働契約法
・あっせん対応
労働基準監督署の調査とは
労基署が行う調査とは「臨検」と呼ばれる調査で、労基法101条第1項で以下のように定められています。
※注釈
1)臨検・・・監督官が法令違反の有無を確認する目的で事業場への立ち入り調査を行うこと
2)帳簿及び書類の提出・・・法定帳簿、就業規則、協定書、勤怠等書類
3)尋問・・・事業主及び従業員に対して陳述を求めること
臨検の種類
臨検には以下の種類があります。
(1)定期監督
(2)申告監督
(3)災害時監督
(4)再監督
(1)定期監督
計画的な監督指導として、労働時間、労災等これまでの状況について全体的な指導計画の一環として行われるものです。
(2)申告監督
労働者からの電話や投書、窓口相談の申告で行われるものです。このケースはよく「労基に駆け込まれた」などと言う表現で耳にすることがあるかもしれません。
労働基準法では監督機関に対して申告することができる旨を定めていますので、申告したことを理由として労働者に対して解雇や不利益な取り扱いをしてはなりません。
また申告監督のケースでは行政がある程度証拠を押さえていることが多く、いきなりやって来ることが多いです。
(3)災害時監督
労災発生(業務災害)に対して実施されるもので、原因究明や再発防止を目的に行われるものです。
臨検は重大災害の場合だと来るまでに時間が経過している事がありますが、死亡事故の場合だとすぐにやって来ることが多いです。
(4)再監督
監督指導後に是正状況の確認の為、再度監督指導にくることです。
ある会社の臨検事例
ここである事例を紹介します。
A株式会社は臨検の結果、以下のような是正指導を受けました。
【主な是正指導内容】
・36協定未締結
・残業代未払い
・休憩未取得
・年次有給休暇5日取得制度なし
・フレックス協定未締結
・1ヶ月100時間超の残業
・定期健康診断未受診者あり
・衛生推進者未選出 他
上記是正に対して、結果として数百万円の未払い残業代の支払いが発生してしまいました。
指導内容を見ていると労働基準法違反から労働安全衛生法まで多岐にわたる指導が発生したことが分かります。
また、是正された内容は適正に運営する為の手続きや書類の作成などの不備によるものもあります。
法律の範囲内だったとしても適法に運用がされていなければ、大きな代償が伴うという事に注意が必要です。
年金事務所編
続いて社会保険各法の行政調査をいうと「年金事務所」の調査です。
最近の年金事務所調査では法改正に伴う調査として以下の内容が急増しています。
1)適用拡大
2)未適用摘発
3)加入者、報酬額の適正申告確認
(1)適用拡大
2024年10月から51人以上の事業所(特定適用事業所)では、パートなどの社会保険加入の対象範囲が広がっています。要件を満たす場合は対象者をきちんと加入させているかが確認されます。
(2)未適用摘発
法人登記をされいるにも関わらず社会保険の加入手続きがされていない事業所に対しても調査対象とされます。
加入対象者がいない場合や、事業活動をしていない(休眠)等の理由がある場合はその証明を求められます。
(3)加入者、報酬額の適正申告確認
加入漏れがないか、報酬額の申告(資格取得時や算定基礎届)は適正か、報酬額に変更があった際の手続き(月額変更届)漏れがないか等も調査対象とされます。
社会保険の時効は2年間、遡及された場合は何百万の保険料?!
とある会社では調査時にきちんと対応しない、虚偽など不誠実な対応をした結果、2年前に遡及して手続きと保険料清算の指導を受けた事例があります。ご存じの通り社会保険料は報酬比例で保険料が決まりますので、そこそこ人数がいるケースだと保険料は数百万円になることも珍しくありません。
社会保険では特に「適用拡大」の法改正の影響が大きいです。改正内容を適切にキャッチしていないと加入漏れにつながってしまいます。また、申告する方報酬に含めるもの・含めないものなどもルールが細かいので、理解するのも一苦労です。
自社で手続きなどを行っている場合は、日頃の業務が適正に行われているか改めて点検してみて下さい。
まとめ
今回は行政調査の代表格である「労働基準監督署」と「年金事務所」の内容について触れました。
実際に調査となると慌ててしまったりするかと思います。しかし、指導された事例内容を見ると日頃の対応によって回避できるものも少なくないと感じた方もいらっしゃるかと思います。
行政調査に正しく対応するには労働法や社会保険各法に精通した社労士のフォローは欠かせません。
行政調査が来た際は先ずは慌てずに落ち着き、すぐに専門家(顧問社労士)へ報告することを忘れないで下さい。
お問い合わせ
Office Asouでは労務管理や法改正対応、日頃の手続き業務等に不安を感じている企業様に対して、積極的にサポートさせて頂いております。
・手続きが煩雑で対応が大変
・書類の作成がめんどくさい
・労務管理が適切に行えているか不安 など
上記のようなお悩みがある企業様、ぜひ一度弊所へお気軽にご相談下さい。
お問い合わせはこちら