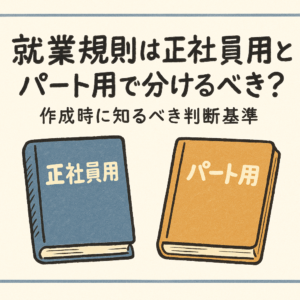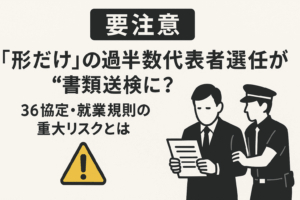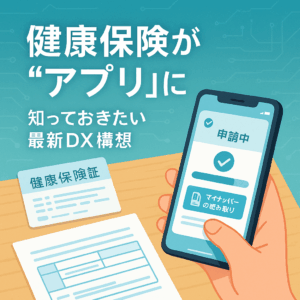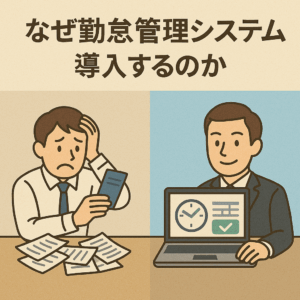【人事労務担当者必見】36協定書と36協定届の違い理解できていますか?

こんにちは、社会保険労務士の安生です。
会社が労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合には36協定が必要なことは皆さんご存じかと思いますが、「36協定」関連の書類には、「協定書」と「協定届」の2種類あることはご存じでしょうか。「書」と「届」で名前が似ていますが、実は「36協定書」と「36協定届」は異なる書類になります。
今回は「36協定書」と「36協定届」について分かりやすく解説します。
また違反した場合にどうなるのかについても解説しますので、これを機会に36協定についての認識と自社の運用は大丈夫かを是非確認してみてください。
36協定書と36協定届は何が違う?
「36協定書」は、労使が時間外労働・休日労働に関する事項について協議し、合意に至った内容が記載されます。
法定のフォーマットがあるわけではないので自由に記載することができます。
ただ、労使の合意書になるため、労使双方が署名ないしは記名押印をして、当該事業場に保存する必要があります。
一方「36協定届」は上記で作成した「36協定書」の内容を会社が管轄の労基署に届け出るための書式です。
現在36協定届は署名ないし記名押印が廃止されていますので、原則不要となっています。
記載事項に漏れがあると無効になってしまうため、実務上は厚生労働省のホームページでダウンロードした様式を使用するのが一般的です。
「36協定書」と「36協定届」は本来別々の書類なので、協定書と協定届をそれぞれ作成する必要があります。
ただし、「36協定書」と「36協定届」を兼ねる場合には、合意がなされたことが明らかになるようにしなければいけないため、労使双方の署名または記名押印が必要となります。
厚生労働省が作成している36協定届の様式には、使用者と労働者代表の(印)の記載がありません。協定書を兼ねる場合は労働者代表の署名ないしは記名押印の漏れがないように注意しましょう。
36協定の届出
36協定は原則として、事業場ごとに作成しなければなりません。(本社、支店、工場など)
したがって、各事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ届け出ることになりますが、一定の条件を満たせば本社で一括して届け出ることも可能です。
一括での届出を可能とする要件は、「本社と全部または一部の本社以外の事業場にかかる協定の内容が同じであること」です。「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地」「労働者数」以外の事項が全て同一でないと一括はできません。
なお、「一括届出」はあくまでも「届出」を一括で行うだけで、締結自体は事業場ごとに行う必要があります。
届出の時期
基本的なことですが、労働基準法では法定労働時間を超える労働を禁止しています。36協定はその法定労働時間を超える残業や法定休日労働を例外的に認める(免罰)という性質があります。
そのため例外的に認めてもらうためには労働基準監督署へ届け出ることが必須となります。
したがって、36協定を締結して適法な状態で残業や休日労働をさせる為には、36協定で取り決めた有効期間の開始前に届け出を完了させなければなりません。
また有効期間を過ぎると、その36協定は無効になります。
毎年同じ時期に届け出が必要になりますので忘れないようにしましょう。
届出の方法
事業場を管轄する労働基準監督署へ持参して届け出るのが一般的です。届け出用の原本と写しを用意して、原本は労働基準監督署に提出します。(写しに労働基準監督署の受理印を押してもらえるので、それを控えとして持ち帰ります。)
郵送で提出することも可能ですが、切手を貼った返信用封用を同封しておかないと写しは返送対応してもらえません。
郵送で提出する際は返信用封筒を同封するのを忘れない様にしましょう。
なお、届出内容に不備があった場合は受理されずに返戻されてしまいますので、提出は余裕をもっておこないましょう。
届出の保存
36協定は届け出るだけでなく、労働者に周知しなければなりません。
書類の保存方法は特段、法律での定めはありませんが紛失などがないようにファイリングして適切な場所に保管しましょう。(周知するのは労働基準監督署の受理印のある原本ではなく、コピーを閲覧用に準備するのが良いと思います。)
労働者に周知する方法としては下記のいずれかの方法が推奨されています。
1.常時各事業場の見やすい場所へ掲示するか備え付けておく
2.書面で労働者に交付する
3.磁気テープや磁気ディスクなどの電子媒体に記録し、労働者がその内容を確認できる
4.機器を常時配備する
周知されていない場合、36協定は無効となります。
また周知義務に違反すると労働基準法第120条に基づき30万円以下の罰金が科されることもあるため、周知を徹底するようにする必要があります。
36協定違反の具体例
36協定に違反した場合の具体例は次のようなものがあります。
- 36協定届を作成しないまま、労働者に残業や休日出勤をさせた。
- 36協定届を作成はしたものの、届出を失念していた。
- 36協定で定めた延長の限度時間を超えた時間や日数を、残業・休日出勤させた。
前述の行為はすべて労働基準法違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
こんな場合どうする?
【36協定の限度時間を超えそうな場合】
36協定の限度時間は厳守です。計画的に仕事をしようと思っていても、メンバーに欠員が出てフォローしないといけない、取引先から急に仕様変更の連絡が来る、など想定外の事態が起こりうるでしょう。
しかし、どのような理由があろうとも限度時間は守らねばなりません。
使用者は労働者の労働時間を適正に把握する義務があるので、勝手に労働者が残業していたという使用者の主張は通りませんので、適正に労働時間管理を行った上で限度時間を超えないようにチェックしましょう。
【限度時間を超えてしまった場合】
当然に労働基準法違反となりますので、労働基準監督署の調査が入った場合、是正勧告を受けることになっても申し開きできません。
緊急事態で、とか、繁忙期だったんです、などは理由として認められませんので、二度と同じ事態に陥ることのないように対策を講ずるべきです。
まとめ
36協定は、従業員1人が1分でも残業をする場合は作成や届出が必要になります。
残業発生には様々な要因があると思いますが、残業の抑制を労働者任せにしていると、後になって労働者から残業代請求を受けたり、長時間労働による健康被害を訴えられるようなリスクが発生し、会社が責任を負うことになる可能性が高いです。
「早く帰るように」と口頭注意をしていても、それ以上対策を取らなければ「業務過多で残業をしなければ仕方なかった」という労働者の言い分が認められてしまう可能性もあり得ます。
きちんと労働時間の管理をおこない、残業は上司から部下に命じておこなうものであることを周知徹底し、その形式に則った資料(証拠)を残すことが重要です。
お問い合わせ
Office Asouでは労務リスクに不安を感じている企業様に対して、積極的にサポートさせて頂いております。
・労務相談や規則類の作成について誰に相談すればよいのかわからない
・毎年の36協定の提出期限を管理するのが煩わしい
・書類の書き方が分からない、提出がひと手間 など
上記のようなお悩みがある企業様、ぜひ一度弊所へお気軽にご相談下さい。
お問い合わせはこちら