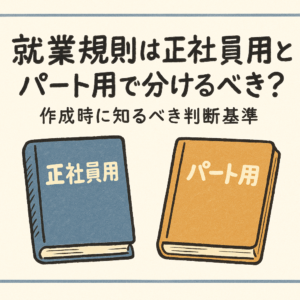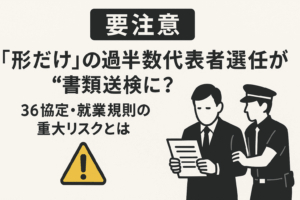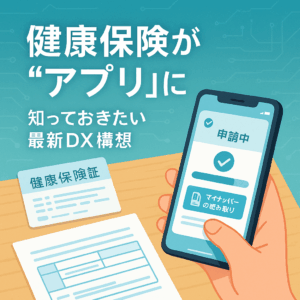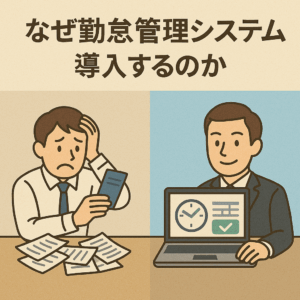料金だけで選ぶと失敗する!顧問社労士選びで押さえるべき3つの重要ポイント
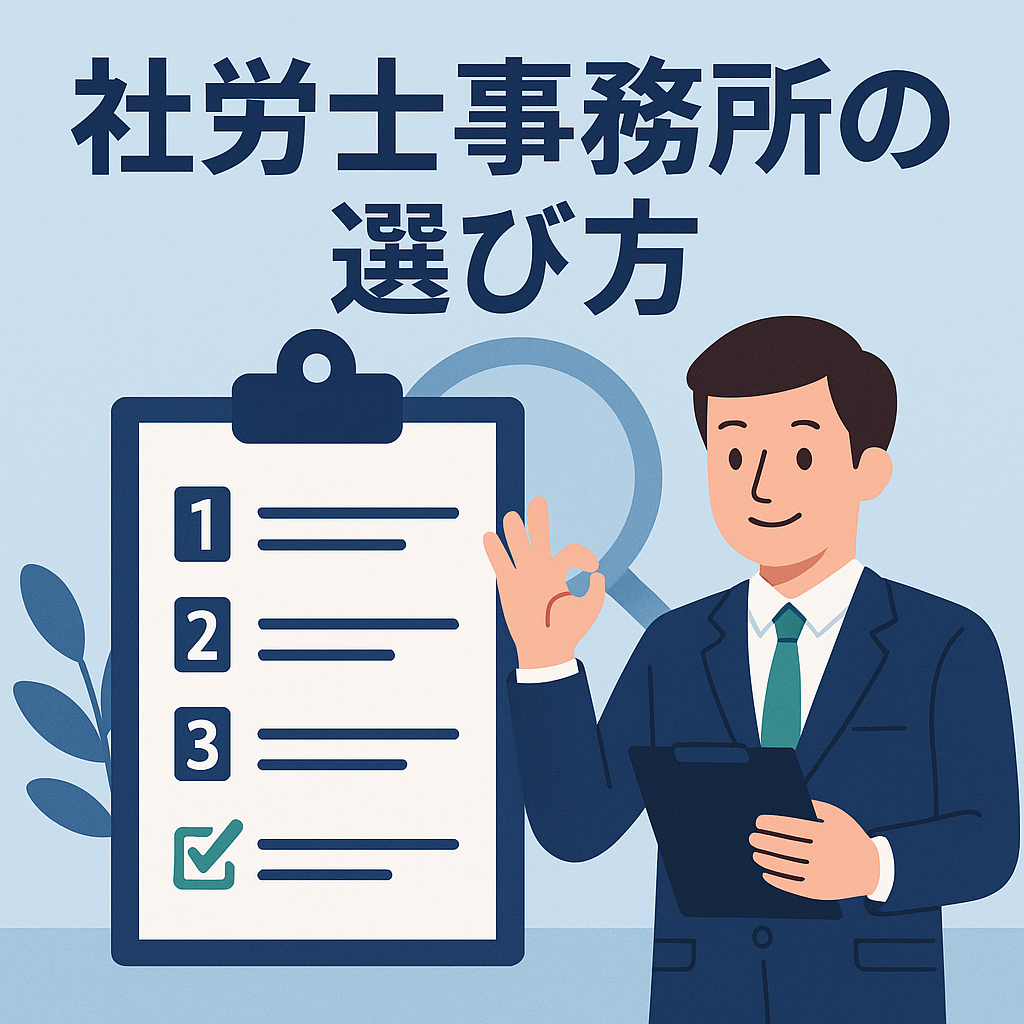
こんにちは、社会保険労務士の安生です。
社労士に業務を委託することは、企業の労務管理を円滑に進める上で非常に有効な手段です。しかし、数ある社労士事務所の中から自社に最適なパートナーを見つけるのは、簡単なことではありません。契約後に「思っていたのと違った…」という事態を避けるためにも、以下の3つのポイントをしっかり押さえておきましょう。
何のために委託するのか?目的を明確にする
まず最も重要なのは、「なぜ社労士に業務を委託したいのか」という目的をはっきりさせることです。
目的が曖昧なまま契約してしまうと、期待していたサービスが受けられず、不満が生まれる原因となります。
社労士事務所が提供するサービスは多岐にわたります。例えば、以下のようなものが挙げられます。
労務手続きの代行: 社会保険や労働保険に関する煩雑な手続きを任せたい。
法令遵守(コンプライアンス)のサポート: 法改正に適切に対応し、労務リスクを減らしたい。
助成金の申請代行: 活用できる助成金について提案から申請までサポートしてほしい。
就業規則の作成・見直し: 自社の実態に合った規則を作成したい。
ITツールの導入支援: 勤怠管理や給与計算のDX化を進めたい。
人事評価制度の構築: 公平で納得感のある評価制度で、従業員のモチベーションを高めたい。
特に助成金については、積極的に提案・申請代行を行う事務所と、そうでない事務所の差が大きい印象です。
もし助成金の活用を視野に入れているのであれば、必ず事前に確認しましょう。
また、会社と社労士事務所の関わり方についても、「こちらから相談した時だけ対応してほしい(受動的)」のか、「定期的に面談などを設けて、積極的に課題解決の提案をしてほしい(能動的)」のか、どちらのスタイルを望むかによっても、選ぶべき事務所は変わってきます。
いざという時も安心!事務所の人員体制を確認する
社労士事務所は、社労士一人で運営しているケースも少なくありません。社労士1人体制の事務所が決して悪いわけではありませんが、担当の社労士が万が一、病気や事故で対応できなくなった場合、業務が滞ってしまうリスクがあります。そうした事態に備え、リスクヘッジがしっかりしている事務所を選ぶことが重要です。
具体的には、「複数の社労士が在籍している」や「一人の顧客に対して、複数名の職員で担当するチーム制をとっている」等があります。
また、社労士1人であっても「緊急時には他の社労士に引き継げる体制を整えている」事務所もあるかと思います。
上記のポイント等を事前に確認しておくと良いでしょう。
ストレスフリーな関係を築く!コミュニケーション方法をチェック
急速にデジタル化が進む現代において、コミュニケーションの手段は多様化しています。顧問社労士と円滑に連携するためにも、自社が希望するコミュニケーション方法に対応しているかを確認しましょう。
連絡手段: 対面、電話、チャットツール、メールなど、どの方法をメインにしたいか。
納品物の形式: 書類は紙で欲しいのか、PDFなどのデータで欲しいのか。
特に、税理士事務所と違って、社労士事務所では定期的な面談を行わないケースも多いです。もし定期的な訪問や面談を希望する場合は、その要不要や、追加費用の有無についても、契約前にしっかりと確認しておくことが大切です。
まとめ
顧問社労士を選ぶ際には、今回ご紹介した「委託目的の明確化」「人員体制」「コミュニケーションの方法」という3つのポイントを事前に見極めることで、契約後のミスマッチを大幅に減らすことができます。
ぜひ、自社にとって最高のパートナーを見つけるための参考にしてください。
お問い合わせ
Office Asouでは積極的に顧問契約を承っております。
・起業したが何を手続きしたらいいか分からない
・初めて社員を採用する予定があるが何を準備したらいいか分からない
・自社で手続きをする社員がいるが属人化していて退職時のリスクを抱えている
・人事労務に関する業務を減らしたい
・いつでも相談できる専門家が欲しい など
上記のようなお悩みがある企業様、ぜひ一度弊所へお気軽にご相談下さい。
お問い合わせはこちら