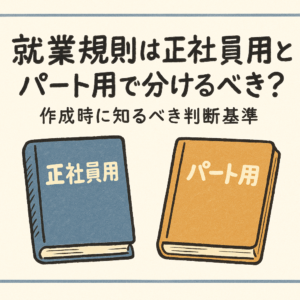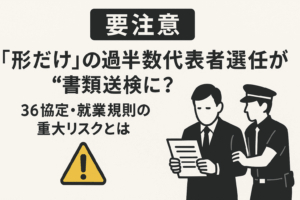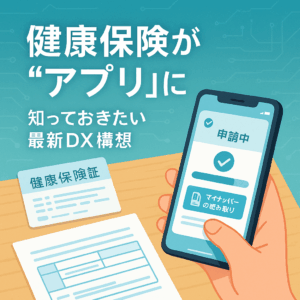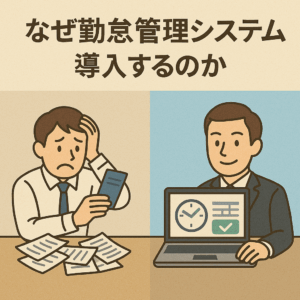社労士と顧問契約を結んでいない会社が見落としがちな労務手続き3選
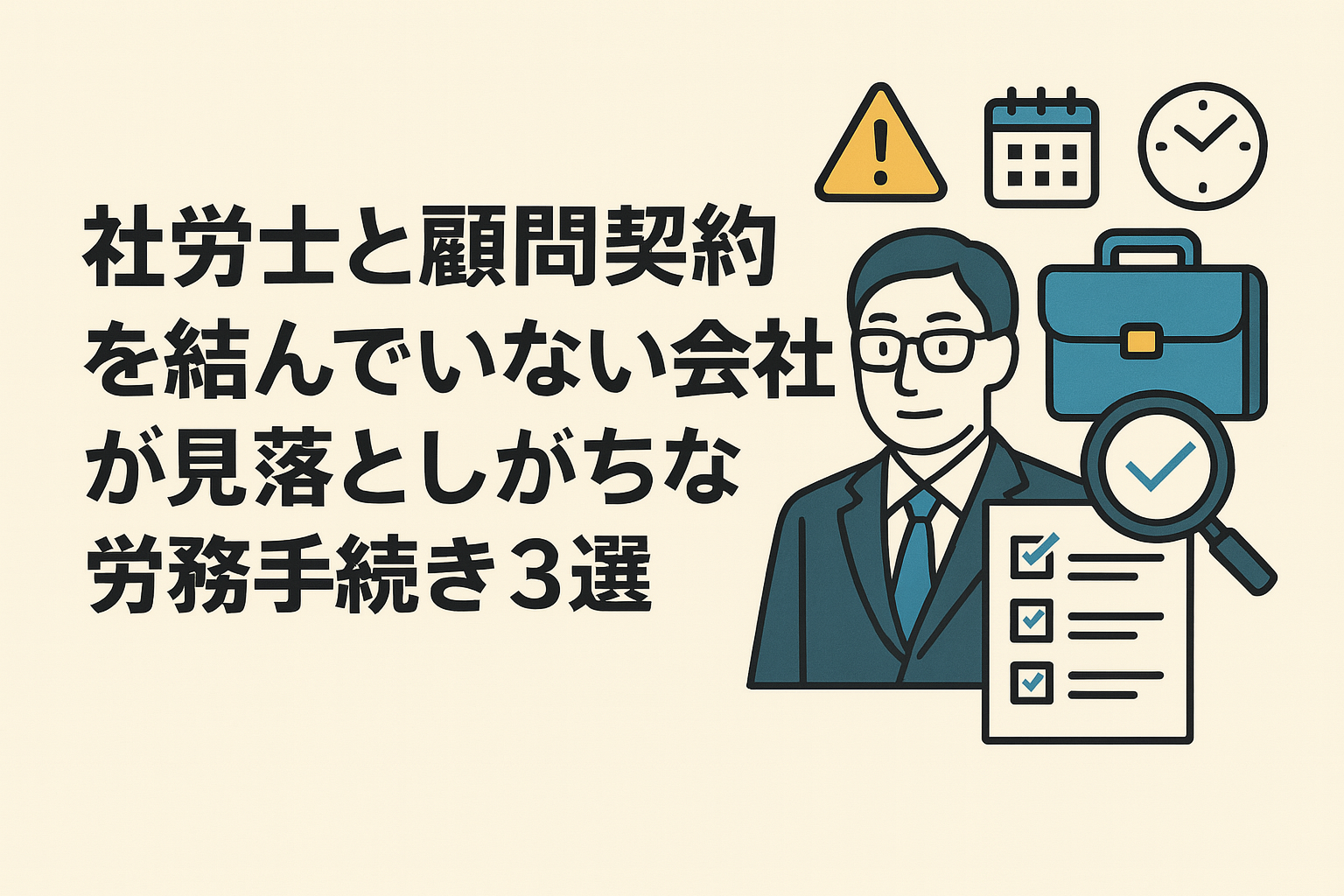
こんにちは、社会保険労務士の安生です。
多くの会社では税理士と顧問契約を結んでいる会社は多い一方、社会保険労務士と顧問契約を結んでいる会社はあまり多くないのが実情かと思います。
「うちは従業員も少ないし、労務管理は自社で十分」――そうお考えの経営者・人事担当者様も多いのではないでしょうか。もちろん、日々の業務が円滑に進んでいれば、社会保険労務士との顧問契約は必須ではありません。
しかし、専門家がいないからこそ、思わぬ手続き漏れが発生しやすいのも事実です。
今回は、社労士に依頼していない企業様が特に見落としがちな3つの重要な労務手続きについて、そのリスクと対策を分かりやすく解説します。気づかぬうちに法令違反とならないよう、この機会に自社の体制を再確認してみましょう。
「36協定」の締結・更新、忘れていませんか?
従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合、必ず必要になるのが「36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)」です。特に、創業間もない企業や少人数の事業所では、この協定の存在自体を知らなかったり、手続きを忘れていたりするケースが散見されます。
36協定の有効期間は最長1年で、毎年更新して労働基準監督署に届け出る必要があります。
もし、この手続きを怠ったまま残業をさせてしまうと、法律違反となり罰則の対象になる可能性もあります。
タスク管理ツールなどで更新時期をリマインドする、あるいはこの手続きだけをスポットで社労士に依頼するなど、確実な管理体制を構築しましょう。
その労働時間制度、本当に合法?「変形労働時間制」の落とし穴
顧問契約のご相談時にどのような労働時間制を導入されているかを伺うと「1ヶ月変形労働時間制」や「1年単位の変形労働時間制」、「フレックスタイム制」など、法定労働時間を超える柔軟な働き方を導入されている話を聞きます。
しかし上記のような変形労働時間制を導入するにあたり必要な手続きを踏んでいないケースが目立ちます。(就業規則への記載や協定届の提出等が必要です。)
「うちは特殊な働き方だから」という認識だけで、適切な手続きを踏んでいない状態では、どこからが時間外労働になるのか計算の根拠が曖昧になり、従業員への残業代未払いといった重大な問題に発展しかねません。自社で採用している労働時間制度が適切か不安な場合は、一度、労働基準監督署や社労士に相談することをお勧めします。
給与は変わったのに保険料はそのまま?「社会保険の月額変更届」
昇給や役職手当などの支給などにより、従業員の固定給に大幅な変動があった場合、社会保険料を見直すための「月額変更届」を提出しなければなりません。
この手続きは、給与が変動したからといって自動的に行われるものではなく、企業側からの届け出が必要です。手続きを忘れてしまうと、将来の年金額や健康保険の給付額(傷病手当金など)に影響が出るだけでなく、年金事務所の調査で発覚した際に、過去に遡って不足分の保険料を一括で徴収されるといった事態にもなりかねません。
顧問社労士がいれば定期的なチェックをしてもらえますが、自社で管理する場合は、給与計算の都度、対象者がいないかを確認する習慣をつけましょう。
まとめ
労務管理を自社で行うことは、決して間違いではありません。しかし、今回ご紹介したような「漏れやすい手続き」が存在することも事実です。これらの手続きを確実に実施することが、従業員との信頼関係を築き、健全な企業経営を続けるための第一歩となります。
本コラムを参考に、ぜひ一度、自社の労務管理体制を見直してみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ
Office Asouでは継続的な伴奏支援をさせて頂き、企業様のお困りごとを解決させて頂く顧問契約を承っております。
・社内での労務管理体制に不安を感じている(人材不足、教育不足等)
・手続き等の事務作業が負担になっている
・手続きは自社で行うが専門家のアドバイスが欲しい
上記のようなお悩みがある企業様、ぜひ一度弊所へお気軽にご相談下さい。
お問い合わせはこちら