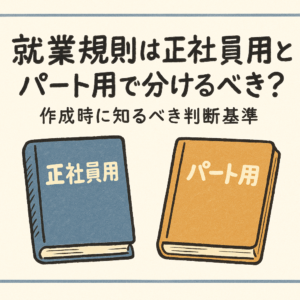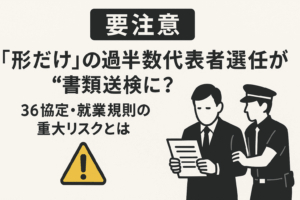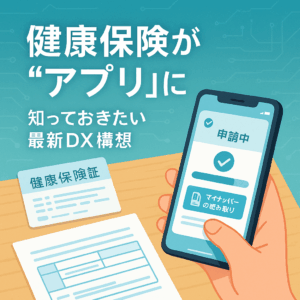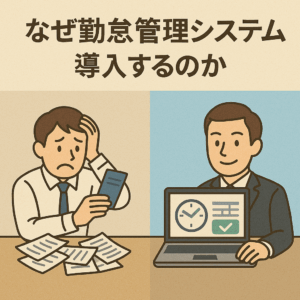給与計算システム選び、会計ソフトと揃えるべき?社労士が解説する3つのポイント
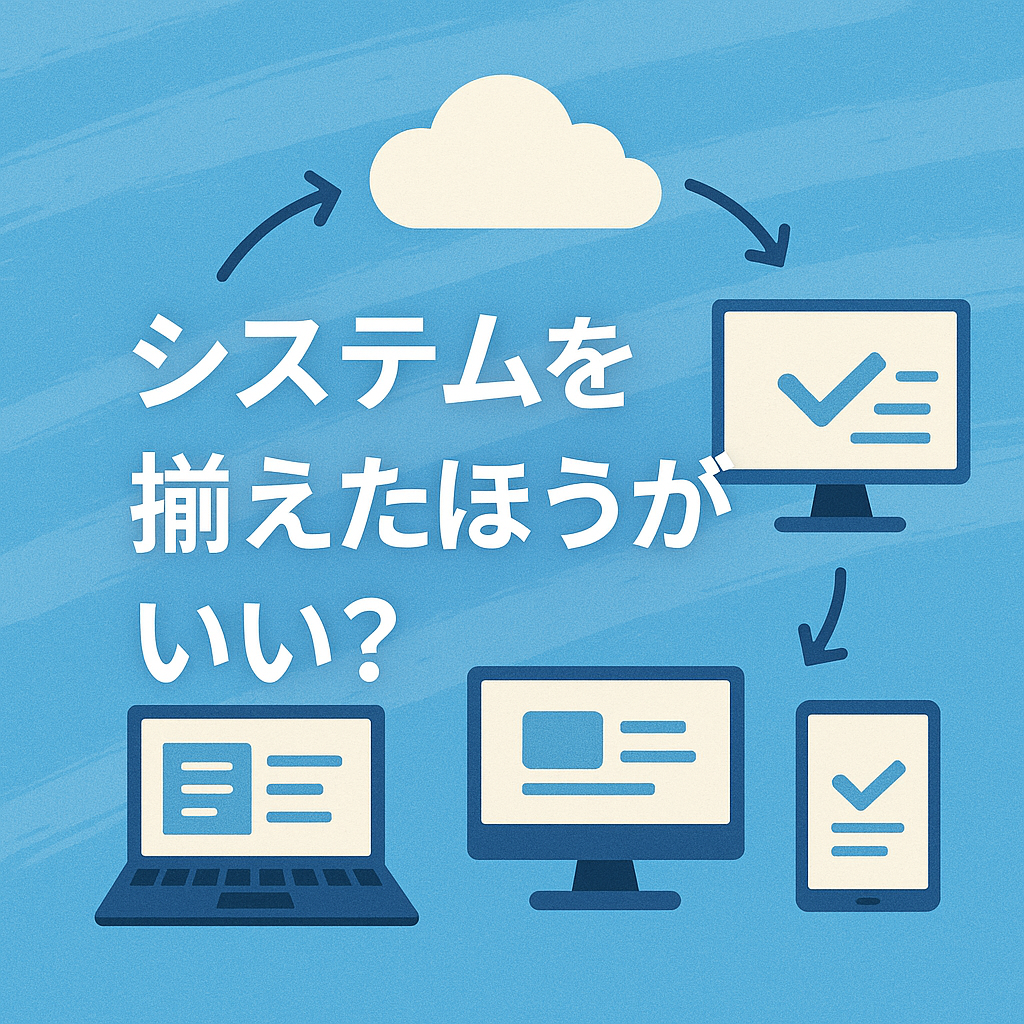
こんにちは、社会保険労務士の安生です。
システム導入を検討する際に会計システムと同じシリーズで揃えた方が良いか?という質問をよく頂きます。
バックオフィス担当者であれば、一度は悩んだことがあるのではないでしょうか。
今回は、給与計算システムを選ぶ際に本当に重視すべきポイントを、社労士の視点から解説します。
会計と給与計算、同じシリーズで揃えるメリットは?
多くの会計ソフトメーカーは、同シリーズの給与計算システムも提供していることが多く、連携のスムーズさをアピールしています。具体的には、以下のようなメリットが挙げられます。
割引価格の適用:セットで導入することで、価格的なメリットが生まれる可能性があります。
経費精算との連携:従業員が申請した経費を、給与に簡単に反映させることができます。
会計システムへの自動入力:給与計算の結果(人件費や福利厚生費など)を、ボタン一つで会計システムに登録できます。
これらのメリットは、確かに魅力的です。しかし、個人的には「必ずしも同じシリーズにこだわる必要はない」と思いっています。
「連携」よりも大切な、給与計算システム選びの2つの軸
会計システムとの連携よりも、優先すべき2つの点をお伝えしたいと思います。
①勤怠管理システムとの連携
従業員一人ひとりの正確な労働時間や日数を把握することは、給与計算の根幹です。
その為、現在利用している、あるいは導入を検討している勤怠管理システムとスムーズに連携できるか(API連携やCSV連携)は、必須条件と言えるでしょう。
②自社の給与規定への対応力
給与計算は、単に人件費を会計システムに登録するための作業ではありません。残業代の計算方法、手当の支給条件、端数処理など、企業にはそれぞれ独自のルールがあります。こうした細かい給与規定に柔軟に対応し、正確な給与計算ができるかどうかが、最も重要なポイントです。
まとめ
会計システムとの連携は、確かに便利な機能です。しかし、そのために自社のルールに合わないシステムを選んでしまっては本末転倒です。
給与計算システムを選ぶ際は、まず「自社のルール通りに計算できること」、そして「勤怠管理システムとスムーズに連携できること」を最優先に検討しましょう 。
その上で、会計システムとの連携機能も考慮に入れる、という順番が最適なシステム選びの近道と言えます。
お問い合わせ
Office Asouでは人事労務の業務効率を目指したい企業様へのシステム導入支援を承っております。
・システムがインストール型なのでクラウドに移行したい
・システム導入をしたいがどのシステムを選んだらいいか分からない
・システム設定がきちんとできるか不安
上記のようなお悩みがある企業様、ぜひ一度弊所へお気軽にご相談下さい。
お問い合わせはこちら