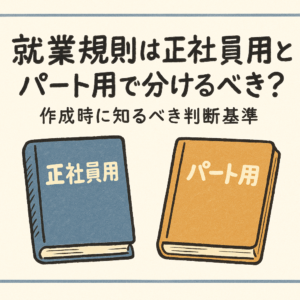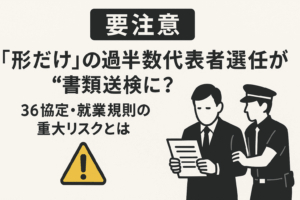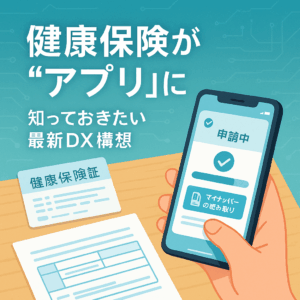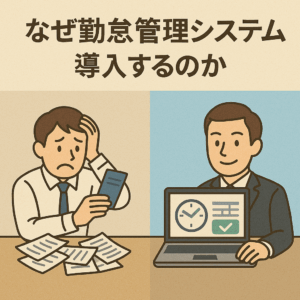【社労士解説】2025年4月改正|育児休業給付が手厚く!新設「出生後休業支援給付金」で“手取り10割”実現へ

皆さん、こんにちは。社会保険労務士の安生です。
2025年(令和7年)4月1日より、雇用保険の育児休業給付制度が大きく変わりました。今回の改正では、産後間もない時期の休業取得を経済的に支援し、男女双方の育児休業取得をさらに促進することを目的とした「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が創設されました 。
今回は、出生後休業支援給付金を中心に、制度改正の要点を分かりやすく解説します。企業の人事労務ご担当者様、そしてこれからお子様を迎える従業員の皆様、ぜひご一読ください。
※育児時短就業給付金についての詳細をお知りになりたい方はこちらをご覧下さい。(厚生労働省出典)
改正の背景 男性の育休取得率アップを後押し
近年、政府は「男性の育児休業取得率の向上」を重要政策として掲げています。
しかし、現実には「収入が減るのが不安」「周囲に遠慮して休みづらい」といった声が根強く、取得率は依然として課題とされています。こうした声に応える形で、2025年4月から給付金が手取り10割相当まで引き上げられる制度が導入されました。
新設「出生後休業支援給付金」で手取り10割相当の支援へ
今回の改正で新設された「出生後休業支援給付金」は、従来の「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」に上乗せして支給されるものです 。
支給の仕組み
この新しい給付金を活用することで、休業開始前の賃金の最大80%が給付金として支給されることになります。
- 出生時育児休業給付金(または育児休業給付金): 休業開始時賃金日額 × 休業日数 × 67%
- 出生後休業支援給付金: 休業開始時賃金日額 × 休業日数 × 13%
合計で80%の給付率となります 。
育児休業中は健康保険料や厚生年金保険料も免除され、給付金は非課税。これにより実質的に休業前と同水準の手取り収入が確保されるという仕組みなっています。
支給要件
出生後休業支援給付金を受けるためには、被保険者本人と配偶者の両方が一定の要件を満たす必要があります。
1. 被保険者本人の要件
対象期間内に、通算して14日以上の産後パパ育休(出生時育児休業)または育児休業を取得し、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受けること 。
【対象期間】
父親の場合: 子の出生日(または出産予定日)から8週間以内
母親の場合: 子の出生日(または出産予定日)から16週間以内
2. 配偶者の要件
被保険者の配偶者が、子の出生後8週間以内に通算14日以上の育児休業を取得していること、または、子の出生日の翌日時点で「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当すること。
「配偶者の育児休業を要件としない場合」の例
・配偶者がいない場合
・配偶者が無業者や自営業者、フリーランスなど雇用保険の被保険者でない場合
・配偶者が産後休業中である場合
※父親が取得する場合、母親は産後休業中であることが多いため、この要件を満たすケースが多くなります
「出生時育児休業給付金(産後パパ育休)」と「育児休業給付金」
新しい給付金のベースとなる、既存の2つの給付金についても改めて確認しておきましょう。
出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
・子の出生後8週間の期間内に、合計4週間(28日)を限度に2回まで分割して取得できます。
・休業中の就業は、休業期間に応じて定められた日数・時間内(最大10日または80時間)である必要があります。
育児休業給付金
・原則として1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得可能)を取得した場合に支給されます 。
・今回の改正により、この育児休業給付金を受ける場合でも、子の出生後の一定期間内に14日以上の休業を取得し、配偶者の要件を満たせば、出生後休業支援給付金の対象となります 。
申請手続のポイント
出生後休業支援給付金の申請は、原則として「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の申請と同時に、一枚の申請書で行います 。
【提出者】
原則として事業主が手続を行います。(本人の希望があれば被保険者本人が提出することも可能)
【提出先】
事業所の所在地を管轄するハローワーク。
【主な添付書類】
賃金台帳や出勤簿など、休業の事実や賃金の支払状況を確認できる書類 。
母子健康手帳など、育児の事実、出産予定日、出生日を確認できる書類。
※出生後休業支援給付金を申請する場合、配偶者の状況を証明する書類(住民票の写し、配偶者の育休取得を証明する書類など)が別途必要になります。
まとめ
今回の育児休業給付制度の改正、特に「出生後休業支援給付金」の創設は、産後の大変な時期における従業員の経済的な不安を和らげ、男女を問わず育児に参加しやすい環境を後押しするものです。
企業としては、従業員への周知徹底と、円滑な申請手続のための準備が求められます。特に、配偶者の状況を確認するための書類の案内など、これまで以上にきめ細やかな対応が必要となるでしょう。
ご不明な点や手続きでお困りの際は、当事務所にご相談ください。書類作成から電子申請のサポートまで、幅広くお手伝いいたします。
参考:厚生労働省出典
令和7年4月改訂『育児休業給付制度の案内』(厚労省リーフレット)
お問い合わせ
育児休業給付に関するご質問やご相談は、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら