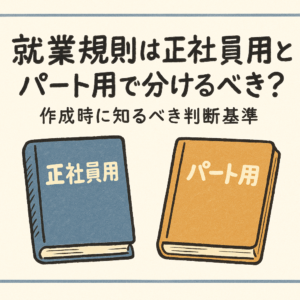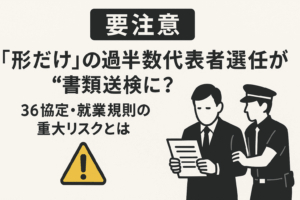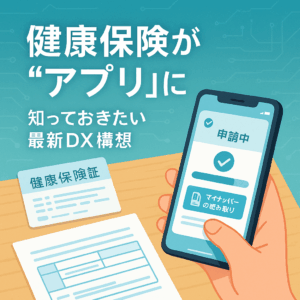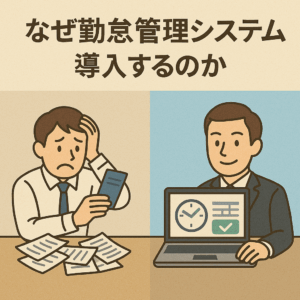勤怠管理システム導入の落とし穴!その「丸め」は違法かも?
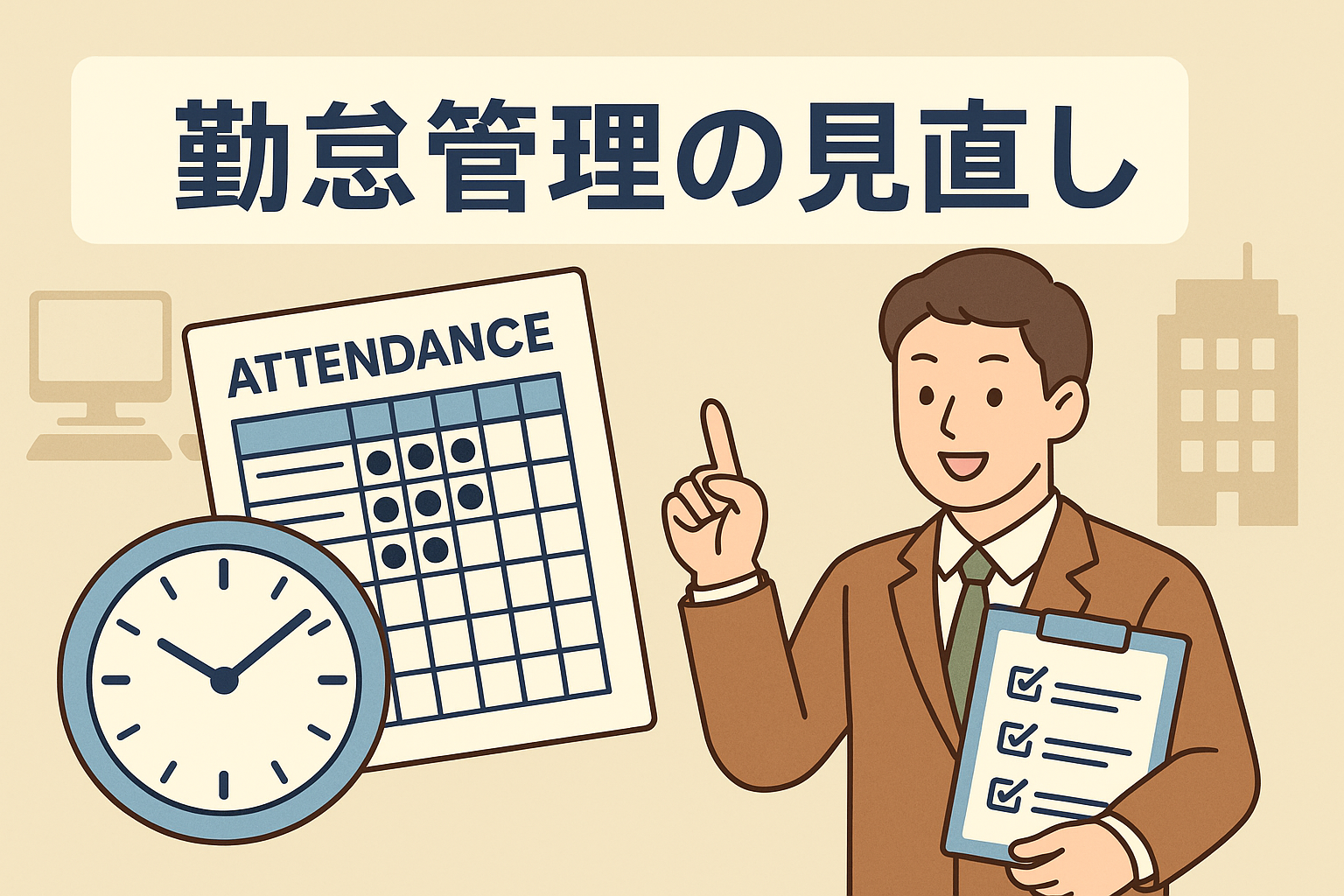
こんにちは、社会保険労務士の安生です。
最近、勤怠管理システムを導入される企業様が増えています。
勤怠管理の効率化や、労働時間の正確な把握は、健全な企業経営に不可欠です。しかし、その導入方法を誤ると、かえって労務リスクを高めてしまう可能性があることをご存知でしょうか?
今回は、勤怠管理の注意点についてわかりやすく解説していきます。
1分単位?それとも丸める?勤怠打刻の基本
多くの勤怠管理システムには、1分単位での集計機能の他に、5分や10分単位で打刻時間を丸める機能がついています。例えば、「8時58分の打刻は9時とみなす」といった設定です。一見、便利に思えるこの機能ですが、実はここに落とし穴があります。
結論から言うと、打刻は1分単位で行うのが原則です。
労働基準法では賃金の全額を払うことが定められています。言い換えれば実際に労働した時間に対して適正に賃金を支払う必要があるという事です。1分単位で記録しなければならない理由は、この労働基準法が根拠です。
そして労働基準法の関連通達ではタイムカード、ICカード、パソコンの使用記録等によって、労働日ごとの客観的記録が可能な手段を用いて把握することが推奨されています。
もし労使紛争に発展した場合、これまで15分や30分単位で丸めていた企業様では未払い残業代が発生し、従業員から請求されるリスクを抱えることになります。
とは言え、紙のタイムカード等で打刻をしていたりすると時間集計の効率化という目的で労働時間の切り捨てや切り上げの処理を行ってきた企業様も少なくないかと思います。
適正な労働時間管理や労働時間集計の業務効率化という面でもシステム導入は非常に有効ですので、1分単位での管理を可能にするためにも勤怠管理システムの導入をお勧めします。
参考:厚生労働省出典
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
始業時刻と終業時刻、それぞれの注意点
始業時刻については、必ずしも1分単位で厳密に管理する必要はない、という考え方もあります。例えば、交通機関の都合で少し早く出社した場合でも、実際の業務開始が定時(例:9時)からであれば、それを丸めるという社内ルールとシステム設定は有効です。
ただし、注意したいのは「黙認」です。始業前に業務を行っている実態があるにも関わらず、それを放置していると、その時間も労働時間とみなされる可能性があります。きちんとルールとして定め、運用することが重要です。
一方、終業時刻の打刻は、1分単位での管理を強く推奨します。
「仕事が終わった後、打刻せず私語をしている社員がいて業務外時間が含まれてしまうので丸めたい」という経営者様のお悩みも耳にしますが、その場合は「業務が終了したら速やかに打刻する」という社内ルールの確立とそれを徹底させることが重要です。
システムとルールの両輪で、適切な勤怠管理を
勤怠管理システムは、あくまでツールです。そのツールを最大限に活かすためには、自社の状況に合わせた適切な社内ルールを整備し、それを従業員に周知徹底することが不可欠です。
自社の勤怠管理に少しでも不安を感じたら、専門家である社会保険労務士にご相談ください。貴社の状況に合わせた、最適な勤怠管理体制の構築をサポートいたします。
お問い合わせ
弊所ではシステム導入に関するご質問やご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら